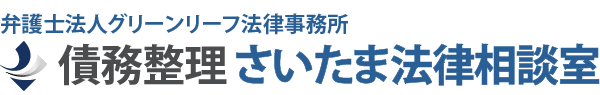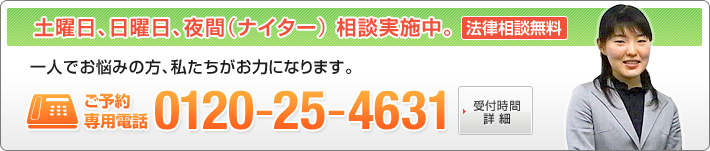紛争の内容
本債務者は、4年前に、自己破産手続き申立て、破産裁判所より、免責の許可を受けています。しかし、それから4年ほどで、多重債務者となり、支払いに窮するようになりました。しかし、破産法は、免責許可の決定確定日から7年内は,破産免責の申立はできない(破産法252条1項10号イ)としていますことから、個人再生手続を申立てられたので、裁判所は同手続き選択の問題、履行可能性などを吟味するために、個人再生委員を選任した件です。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、個人再生委員に選任されると、本再生手続きを解するのが相当か否かの意見を述べることになります。
(1)収入の状況(将来の収入見込み)について
本申立人債務者は、収入状況(その後の収入見込み)については、65歳定年とその後の再雇用の問題がありました。
申立人の勤務先は、65歳定年であり、その後は毎年更新の期間雇用となるとのこと、そして、定年後の期間雇用は、勤務先先輩の給与事情に照らすと、定年前の8割程度の収入となるとのことでした。また、申立人の勤務先企業は、労使間で三六協定を締結しているが、申立人は、土日勤務のシフトを積極的に組み、時間外割増賃金を稼ぎ出しているとのことであり、再雇用後も、現在の収入を支える就労は維持できると見込まれました。
申立人は、年金収入のある実親と同居していましたが、高齢ですので、年金収入が再生計画案に基づく返済中に、その年金が途切れる可能性も検討する必要がありました。
家計全体では、実親の年金収入も計上されていましたが、申立人の収入のみでも家計のやりくりができており、履行テストで4万6000円を負担しても、6万円以上の余剰が出ておりました。上記の収入見込みでも十分可能と見込まれました。なお、これには年2回のボーナス支給も加味されました。
(2)履行テストの金額
本債務者が申立代理人に依頼後、本開始決定がなされるまでの間、およそ1年9か月間の遅延損害金が発生しているものと見込まれました。なお、申立代理人は遅延損害金の利率は調査中とのことでした。
多くの再生債権者からの借入は、10万円を超えて100万円未満の借入金額であることから、利息制限法の遅延損害金として、年26.28%が付されているもの(なお、100万円を超える二口については、21.9%として)として、開始決定日を令和6年7月31日〆として、再生委員において計算したところ、元金、遅延損害金合計は、840万円弱と見込まれまれ、最低弁済額はその2割の、約168万円ほど、月額負担は4万6000円ほどと見込まれました。
そこで、遅延損害金の利率については上限利率で再計算し、それでもなお、履行可能な家計が実現できるものとして、月額4万6000円で履行テストを行うこととしました。
(3) 公租公課の支払い、その他について
申立人には公租公課の滞納はなく、将来の特別出費についても特にその予定はないとのことでした。特に、老親の介護費用の負担が危惧されましたが、申立人は、兄弟姉妹の協力が得られるとのことであり、特段の負担を申立人には生じないと見込まれました。
(4)家計の管理
本申立人は、生活費の支払いをできる限りキャッシュレス化し、デビッドカードを利用して、家計簿は預金通帳履歴から抽出していました。
その抽出に、使途が明確になるように、申立人は、飲食品は極力食品スーパーで購入し、生活雑貨類はドラッグストアを利用しているとのことで、その通帳履歴から分別記帳しているとのことであり、さらに、家計を細かく管理するため、日時ごとに仕分けてつける家計簿のシートをつけてもらいました。
(5)本手続の利用
申立人は、破産免責を受けた後、借入元金500万円強のクレジットカード利用による負債を負いました。しかし、元金全額を完済しなければならないのが原則の任意整理は到底実現しえないことから、本件個人再生申立てに至ったものです。本事件申立代理人からの指導もあって、堅実な家計のやりくりが実現され、さらに、それを継続する意欲も認められました。家計の状況からも、余剰は毎月10万円程度が実現され、今後も見込まれました。
集配車両ドライバーという職業柄、交通事故を惹起する危険性が皆無ではありませんが、これまでの経験からより安全運転を励行することが期待できることから、毎月の安定的な収入が見込まれ、堅実な家計管理により、十分な余剰も出ていること、そして、多めに見込んだ履行テストの金額も十分に賄えるだろうとの予測が立ったため、本手続を解するのが相当との意見を述べました。これを受け、裁判所は、本個人再生手続きを開始する旨決定しました。
(6)債権者の名義変更届出の扱い
ところで、手続中、再債権者の名義変更の届出所が提出されました。再生手続申立前の日付の債権譲渡を原因とするものですが、本手続申立時の債権者一連表には記載されていなかったものです。
よって、債権譲渡人の債権者名での、みなし届出がなされていたことになります。
本手続開始決定は、令和6年7月29日になされました。債権届出期限は令和6年8月19日限りと定められておりますところ、令和6年3月31日付債権譲受人は、同期限までに債権届出をしていませんでした。
この届出は、債権届出期間経過後再生計画案の付議決定前ですが、民事再生法95条1項によれば、再生債権者が、その責に帰することができない事由によって、債権届出期間内に届出ができなかった場合には、その事由が消滅した1カ月以内に限り、その債権の届出ができるとされています。なお、その届出の追完は、小規模個人再生における再生計画案の付議決定がされた後にはできません。
そして、本名義変更届出が、債権届出の追完であるとしても、上記期間内に、その届出ができなかったことの帰責事由のないことの主張は見受けられません。当然ながら、上記債権譲受会社は、開始決定通知を受けていませんので、これをもって、同債権者の責に帰することができない事情があると解することができる(条解民事再生法第3版514頁)ならば、同変更を認めて差し支えないという対応となるとも考えられました。
他方、本債権届出の追完が認められない場合には、債権認否一覧表が提出され、その中に債権者一覧表に記載されていない債権を認める旨の記載がなされた場合(自認債権としての扱い)という方法が考えられました。これは、通常の民事再生手続において自認債権を認める以上、個人再生手続で自認債権を認めない理由はないと考えられるからとされます。
この自認債権として対応の場合、手続内で確定した再生債権と同様、再生計画の履行期間内に同計画に従った弁済を受けることができることになります。
しかし、自認債権には議決権がなく、また、基準債権(法231条2項3号)にも含めることができない。よって、弁済率を算定する基礎とすることもできない。議決権がないから、他の再生債権者にとって不利益になることはない。債権譲渡会社については、実体法上債権者でないこと、本債権届出において異議を留保しているので、申立人においては、当然、異議を述べるのが相当となります。
この届出の扱いについて、裁判所と協議しました。
裁判所によれば、同変更を認めるも、譲渡し債権者の届出債権額以上の債権額については、減縮(放棄ないし取下げ)の了解を得たとし、事実上の、届出名義の変更を認め、手続を単純化しました。
(7)再生計画案の確認
再生委員として、申立代理人から提出された再生計画案の原案を確認し、適切な再生計画となるようアドバイスしました。
そして、債権者に提示された再生計画案に対し、債権者から異議もなく、また、本申立ては履行テストの積み立ても滞ることなく行いました。
本事例の結末
再生委員として、不認可事由が認められないので、再生計画を認可するのが相当であるとの意見を述べました。
そもそも、不同意意見もありませんでしたし、提出された再生計画に基づく36回払いの1回分上回る履行テストの金額を送金し続けてもなお、十分な家計を実現していました。よって、履行可能性は十分であるとしました。
裁判所も、本件再生計画を認可し、同決定は確定しました。
本事例に学ぶこと
本債務者は、破産手続で免責許可決定を受けながら、それを受けて(確定して)から、4年後には、500万円を超える多重債務者となっていた方でした。破産したら、カードは作れない、借金できないと思っていたところ、カード発行審査にとおり、複数カードが保有でき、やはり、カード利用に頼り、使い過ぎてしまったようです。
今回は、再生委員としての関与でしたが、一度破産して免責許可を受けたのに、多重債務者となってしまった方、住宅ローン特則付き個人再生手続きを利用し、再生計画に基づく支払を完了後、数年をして、再度の個人再生手続き利用をしなければならなくなった方の相談が増えています。
当事務所では、二度目の法的債務整理の方の相談もお受けしておりますので、ご遠慮なく、まずは電話相談、そしてご来所での相談を受けられ、ご依頼され、改めての経済的更生の道を歩んでいただければと思います。
当事務所は、このような債務整理を得意としておりますので、きっとお力になれるはずです。
弁護士 榎本 誉